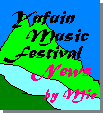 |
アンサンブルの楽しみが息づくまち ~第32回ゆふいん音楽祭へのお誘い~ 青澤隆明(音楽評論) |
| 私はまだ湯布院を知らない。ただ一度、「ゆふいん音楽祭」を訪ねたことがあるだけだ。 それでも、夏が近づいてくると、湯布院のことを思う。それは、僕の住む東京からは遠くにあって、なぜかとても近い場所のように感じる。観光者の勝手な愛着なのかどうかはわからない。けれど、あの風土にしか育まれないだろう、温かな交感はやはり忘れがたいものだ。 それは、真夏の夜の夢のようだった。竹井成美さんのお話と指揮、小林道夫さんのチェンバロ、実力ある演奏家たちのアンサンブルの日々、スタッフの方々の熱意と地元の皆さんのお心づくし・・・・。それから、淡くにじむ灯りのなかで、音楽家やスタッフが集った亀の井別荘での後夜祭の風景を、映画でみた景色のように私は懐かしく想い出している。フェアウェル・パーティーという名の催しでも、まったくお別れの感傷はなかった。私はただ、音楽を愛し、音楽を考え、何よりも日々を味わいながら生きている人々の、情熱とか、ゆとりとか、そうした生きるすべてを豊かさとして、いまここに集まっている熱気を清々しく美しいと感じていた。 音楽祭のあいだ、派手なことはなにひとつなかったけれど、いつまでも覚えている記憶というのは、存外いつもそういうものばかりだ。いい音楽を、みんなで味わった、という充実感のほかに、出会った人々のさまざまな表情が、いつまでも私をこの場所に繋ぎとめている。つまり、途切れることも終わることもなく、真夏のあの熱い夢は、いまも脈々と続いているということだ。 あれから5年がめぐって、いま私の部屋では、「音楽に寄せて」という手作りのCDが流れている。小林道夫さんの端正なチェンバロに耳を澄まし、加藤昌邦さんの水彩画を眺めるとき、その淡い色合いのなかに、ゆったりとした時間が溶け合うようにして、私はゆふいん音楽祭の夏へと想いを馳せる。 バッハもクープランも、ルネサンスもロマン主義の時代も、そうしていまこの現代も、すべてを遠大に包みこむようにして息づく、ゆふいん音楽祭の町と人々の心に、私もここから届いていきたいと願う。 それは、時を急がすことなく、自然と機が熟すのを待つような、心穏やかな想いだ。そして、それらすべてが、思い出や誇張された伝統ではなく、32年も大切に続いてきたゆふいん音楽祭という名の、いまに生きる想いであることを、ほんとうに素晴らしいと思う。 さて、今年の音楽祭だが、長年培われてきたしっかりした構成はやはり変わらない。これはもう、ゆふいん音楽祭様式の古典的な楽章構成と言ってしまってよいだろう。今年はそこに、フランスで学んだフルートの立花千春、バーゼルで活躍し現在は東フィル首席奏者も務めるオーボエの小林裕という木管の名手が明るい彩りを加える。ヴァイオリンの漆原朝子や古典四重奏団といった日本屈指の弦楽器奏者の参加も音楽祭の充実を予感させる。 まずは、気軽に参加できる前夜祭で一足先に音楽家たちに出会い、思い思いに期待を膨らませよう。金曜の昼は、竹井成美と大分中世音楽研究会による「ゆふいん西洋音楽探訪」で、日本の洋楽受容に遠く想いを寄せながら、中世の響きを合唱で堪能する。夜は、音楽祭の総合アドヴァイザーを務める小林道夫のチェンバロをじっくりと聴く。木管の2人も交えて、あまり聴く機会のないソナタも披露。生誕250年を決して騒ぎこそしないが、かの神童の楽譜帖からも演奏され、モーツァルト始まりの光景へと聴くひとを誘う。 土曜の午後は、ピアノに若手の野田清隆を迎え、二人の名手による木管の魅力を味わう。夜は、バッハの夕べ。小林道夫と漆原朝子がソナタで共演した後は、古典四重奏団が『フーガの技法』をじっくりと聴かせる。 そして日曜日。古典四重奏団は今期力を注ぐドヴォルジャークを披露し、漆原朝子と野田清隆が20世紀の古典というべきバルトークの第1ソナタを共演する。音楽祭を長らく支えてきたチェロの河野文昭は、小林道夫のピアノとともにベートーヴェンのハ長調ソナタを弾く。ヴィオラの大野かおるは、小林、野田とともにクルークハルトの「葦の歌」を取り上げる。フィナーレは、モーツァルトの有名なニ短調のピアノ協奏曲K.466を、チェルニー編曲の室内楽版で味わう。充実したアンサンブルがこの夏に深い余韻を刻むだろう。 ひとつひとつのプログラムが、ゆふいん音楽祭でなければ、なかなか聴けない味わい深いものだ。景観と同じで、そこへ足を運ばなければ決してわからない自然な奥行きがある。ゆふいん音楽祭の32年の果実も、まちがいなくそうした感銘のひとつとなるだろう。 |
|
| 第32回ゆふいん音楽祭プログラム | |
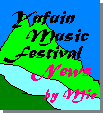 |
|